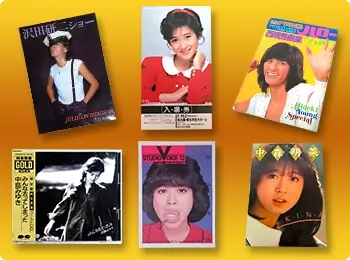Seiko Jazz 0(ゼロ)<下編> ~幻の未発表曲”One of these days” (この、いつの日か)~
9. One of these days 再び
クインシーは私を喜ばそうと思って、一枚のレコードを指しだしてそっと囁きかける。
“マダム、君のレコードだよ。セイコ、お気に入りだろう。最後にもう一度、聞くかね?”
“お願い。”
彼女は腰掛の上で打ちひしがれていた。彼女は考えていた、“私ってなんて馬鹿なの”、と。まさにその瞬間に、存在の反対側、遠くから見ることができるが、決して近寄れないあの別世界で、ひとつの小さなメロディが踊り出し、歌い出した、“私のようにあるべきだ。ハーモニーに合わせて
哀しむべきだ”、と。声は歌う。
One of these days “いつか、そのうち”
is one water way from “それは愛の戯れの中で、
one of those nights “誰もが夢見る
that everyone dreamed of “そうした日々のひとつからの
when love’s in play “一筋の流れ
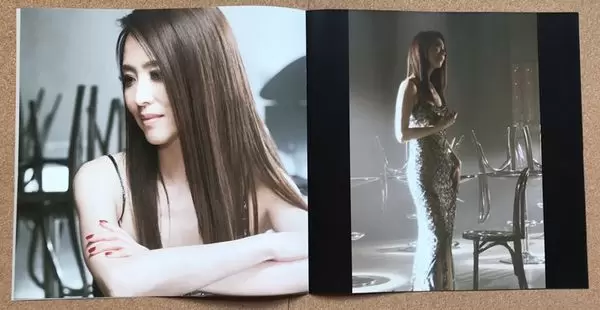
あのPVの中で、ひとり真夜中を彷徨う聖子と老バーテンダー、クインシーの間で交わされた会話はこのようなものではないだろうか?
実はこの文章、20世紀小説のクラッシックのひとつであるJ.P.サルトルの『嘔吐』の結末の一部を、登場人物の名前と出てくる曲の名前をあのPVに合うように入れ代え、細かい箇所をわずかに改変したものなのだ。
どうして、こんな聖子ともこの曲ともまるで無関係に思えることをしたかというと…この小説では孤独の中で彷徨い続けた男が、最後に酒場でレコードから流れるジャズ曲を聴きながら、音楽や小説といった芸術による救いを暗示させて終わっている。ここで流れる曲が”Some of these days”という1920年代後半から30年代にかけて大ヒットした初期ジャズの大ヒット曲で、この小説の中でも何回かの場面で登場する重要な小道具となっている。
題名からもピンとくるだろうが、聖子の”One of these days”の作詞者は、この曲を知った上で、あの詞を書いたに違いないのだ。どちらの曲も基本的には恋人に立ち去られてしまった女の恨み節で、”One of these days”は”Some of these days”の歌詞を踏まえた上でのパロディのような作りとなっている。
後者が“そのうち、あんた、私を失ったことをきっと悲しく思い出すわよ”と歌うの対し、聖子版の歌詞は“私の心はもう知っている、あなたも、すぐそれを知ることになるわ”と歌うといった具合に。PVのストーリー自体も小説のこの結末を踏まえたもの、と考えるのは深読みのし過ぎだろうか?
10.最大の謎、なぜ未発表?
問題はクインシーや聖子、そのスタッフがここまで力を入れて作った曲が今に至るまで未発表である理由だ。クインシーは2000年以降も健在とはいえ、健康状態にはかなりむらがあり、聖子とのコラボに限らず、多くのプロジェクトを完成できずに放り出してしまっているが、一方で、最近ではフランスの女性歌手ZAZ(ザーズ)のプロデュースを3曲だけとはいえ完遂させている。
聖子ファンとしては考えたくもないことだが、出来上がった曲や歌の出来栄えにクインシーが満足できなかったのだろうか?だが、これもおかしい。これほど凝った”One of these days”という曲そのものやPVまで作っておいて-しかもクインシー自身がバーテンダー役で出演だ-、歌の出来栄えに満足できなかったなんてありえるだろうか?
そもそもPV制作時には歌入れも終了して出来栄えはわかっているはずだろう。そして聖子は2011年9月に行われたクインシーのハリウッドのコンサートに出演している。音楽でボツにした歌手を自分のコンサートで歌わせはしないだろう。
つまりボツの理由は別にある。何かアクシデントのような障害が起きたのだ。
考えられるのは、デューク・エリントンの音楽遺産管理人より、デューク自身のピアノ演奏にクレームが入り、使用許可が遂に取れなかったということだ。
曲の使用自体は問題にならないだろう。ただ、本人の演奏の引用となると難色を示すことは大いに考えられるし、理解できなくもない。しかもピアノ演奏にデジタル処理まで施されたのだ。もしかしたらPVのデューク出演にも問題があったのかもしれない。
クインシー側に自分がプロデュースするのだから文句はないはず、といううっかりの油断があった可能性が強い。だが、クインシーは聖子の声とデュークのピアノの融合こそが、この曲の譲れない芯だと考えているから、ピアノ演奏を差し替える、あるいは削除することはプロデューサーとして譲れる一線を越えていた。プロジェクトとしては他にも幾つかの曲が準備されていただろうけど、この曲が無くては、それらも続ける意味はないとされたのだろう。
聖子は2013年のクインシーの日本公演にも前座の日本人枠ではないメインアクトのサプライズゲストとして、パティ・オースチンとのデュエットを披露するという破格の扱いを受けている。既にボツは決まっていたろうから、これはアクシデントにより仕事を完成しきれなかった聖子とファンに対するクインシーなりのけじめだったのかもしれない。
11.そしてSEIKO JAZZへ
One of these days “いつか、そのうち”
is one touch away from “それは遠いあの幾夜の”
one of those nights “ひとつからの手触り”
when all lights go dim “灯がすべてほの暗くなり、
and moonlight, one night ”月明かりの中で、ある夜・・・“
通り一遍の解釈を拒否するような意味深で謎めいた、しかし繊細な歌詞で、演奏のみならず、歌詞まで含めてここまで舞台を演出したMr.Qのデュークへの思い、聖子にかけた情熱、凄まじいまでのものではないか。一体、いつから聖子とMr.Qの関係は始まり、どのように深まっていったのだろうか?
6.聖子とクインシー
そして、結局のところ、”One of these days”は今に至るまで陽の目をみることなく、といって、クインシーと聖子はその後、新たな音楽プロジェクトを始めることもできず、今日に至っている。しかし、”One of these days”での力みを極力排しながら、高音よりは落ち着いた中音域の響きを活かした唱法はその後も、新たな聖子歌唱として引き継がれている。
聖子は2012年にアメリカのスーパーフュージョン(アメリカではスムースジャズと呼ぶ)グループ、ボブ・ジェームス率いるFour Playのアルバム『Esprit de Four』に参加、”Put our hearts together”を歌った。
このどこか似た雰囲気を持つ2曲、これは単なる偶然だろうか? ボブ・ジェームスは実はクインシーファミリーの出身なのだ。ボブの音楽界デビューは、クインシーが審査員をしていた学生のジャズコンテストで優勝したのがきっかけ。1963年のデビューアルバムはクインシーのプロデュースだし、その後もボブはしばしばクインシーの音楽でアレンジを手掛け、長い付き合いがあるのだ。”Put our hearts together”を吹き込みにあたり、”One of these days”を既に知っていた可能性は高い。
そして、近年の『Seiko Jazz 1、2』と続いたジャズ路線。クインシー自身が白状(苦笑)したように、さすがに年齢的に第一線では動けなくなったクインシーが、自身の代わりに弟子とでもいえるマービン・ウォーレンにプロデュースを任せることで、完成しきれなかった”One of these days”を引き継がせたものがSeiko Jazz 2と考えてもいいだろう。
ガチガチのジャズファンたちはSeiko Jazzをそのポップさからジャズと認めるには未だ抵抗感がぬぐえないようだが、モダンジャズ最後の生き証人でもあるクインシーの青春時代には、ジャズは芸術音楽ではなくポップ音楽だったのであり、そんなクインシーから見れば、聖子のようなポップ歌手がセピア色がかったジャズ調アレンジに載せて、アメリカの古いポップスやボサノヴァを歌ったとして、それをジャズと呼んだとしても何ら抵抗はないのだろうし、同時にジャズと呼ばなくても問題にはしないはずだ。
要は、デューク・エリントンが言ったように“音楽には二種類しかない。それは善い音楽と悪い音楽”なのだから。では、聖子の作った音楽は?クインシーの答えは当然、決まっているだろうし、私もいうまでもない。たが、最後の答えは、それぞれのリスナーが自分の感性で判断すればよい。ただひとつ、聖子の今の声に合った歌の魅力を最初に引き出してくれたのはクインシーであって、私はそれを感謝したいと思う。そして、いつか…one of these days…このいつの日か、この曲とセッションの全貌が明らかにされること願っている。
P/S
”One of these days”についての考察は2016年暮れのインターネット上の聖子コミュニティで、この曲が話題になった時、そこに集うみなさんとのやり取りと研究成果の相互発表が基になっている。
けっして私だけで、ここに書かれるような考えに達したのでないことを明確にして、ニドガタリ様、GGさま、コミュの皆様に感謝を捧げます。そして”One of these days”の謎めいた歌詞についてはニドガタリさんがブログでとても興味深い解釈を提示されておられます。
興味のある方、是非とも覗いて見て下さい。
(了)
ボッサクバーナ氏の第1回原稿はこちらです。
特に復帰組の皆さまは感涙モノの力作ですよ!
是非一緒にお読み下さい。
<振り向けば…聖子 再び松田聖子に魅せられて>
良盤ディスクでは、松田聖子をはじめとした、昭和アイドルのグッズを買取中です!
お困りの場合は、ぜひ良盤ディスクへご相談ください!
まずは無料のお見積りだけでも大歓迎です!